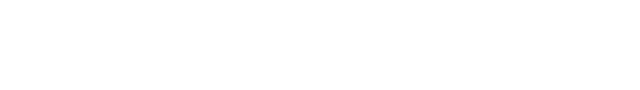診療案内
当院では以下の症状の方に向けた診療を行っております。
呼吸器内科
COPD(慢性閉塞性肺疾患)
COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは、タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝霧することで生じる肺の炎症性疾患です。病気の原因は明確にはなっていませんが、ほとんどが喫煙者であるため、喫煙との因果関係は明らかです。ただし、同じ家族内の発症もみられるため、遺伝性因子も指摘されています。症状は咳や痰、気流閉塞からくる運動時の息切れですが、症状が進むと安静時にも呼吸困難を起こすようになります。また呼吸器症状が少ない場合もあります。病状を進行させないことが大切であり、そのためには禁煙がより重要となります。スパイロメーター(肺機能検査)で程度を判定し、必要に応じて吸入薬による治療を行います。
気管支喘息
気管支喘息は、気道の慢性炎症に基づく気道過敏性の亢進と、発作性で可逆性の咳、喘鳴、呼吸困難を特徴とする疾患です。
急に息ができなくなり、気道が収縮して気管や気管支が詰まり、呼吸の度にのどがゼーゼー、ヒューヒューと鳴るようになります。こうした喘息発作は自然にあるいは薬の吸入などで治まり、症状がない時はふつうに生活できます。原因はしっかりと解明されておりませんが、体質的に喘息の起きやすい人がいて、そこになんらかの条件が加わると発症するとされています。
その条件とは、ウイルスや細菌の感染、自律神経の失調やストレスなどで、これらが引き金となって発作を起こすといわれています。発作の原因としては主なものはアレルゲンで、アレルゲンには非常に多くの種類があります。
その他の原因として、季節の変わり目、気温の変化などによって喘息発作が誘発されます。食べ過ぎや過労、激しい運動、女性では月経や妊娠なども喘息の誘因となります。
スパイロメーター(肺機能検査)、呼吸抵抗測定装置(モストグラフ)、呼気一酸化窒素(NO)測定器などにより評価を行い、主に吸入薬による治療を行います。
肺炎
肺炎とは、病原微生物や細菌が肺に感染し、炎症を起こす病気です。発熱、倦怠感、咳、胸痛などの症状が出現します。
特に病気をもっていない健康な人が、普段の生活や町の中で発症する(市中肺炎と呼ばれる)こともあれば、病院内で何らかの病気をもった人に発症する場合(院内肺炎)もあります。1.細菌性肺炎、2.ウイルス性肺炎、3.マイコプラズマ肺炎、などに分類されます。それぞれに肺炎を引き起こす病原体が異なります。
細菌性肺炎の原因としてもっとも多い(20%~)のは、肺炎球菌です。そのほかインフルエンザ菌、ブドウ球菌、肺炎球菌、緑膿菌、溶血性連鎖球菌などが原因となることもあります。
ウイルス性肺炎は、細菌よりも小さい病原体であるウイルスに感染して起こります。麻疹ウイルス、水痘・帯状疱疹ウイルス、サイトメガロウイルスなどのウイルスが急速に増殖することによって起こる場合もあります。
マイコプラズマ肺炎は、市中肺炎としては肺炎球菌によるものより多くマイコプラズマという病原微生物に感染して起こります。病原菌の種類によって有効な抗生物質を選びます。
間質性肺炎
吸い込んだ空気が気管支を経て、最終的に運ばれるぶどうの房状の袋を「肺胞」といいます。
間質性肺炎は、肺の細胞の壁に炎症細胞が集まって正常構造を壊し、線維化(※)する疾患です。
肺の壁が厚くなるため伸縮しにくくなり、呼吸困難が起こりやすくなります。
診察(聴診)、レントゲン、CTなどで診断を行っていきますが、さらなる精査のために気管支鏡検査(内視鏡検査)や手術を行う場合もあります。
(※)線維化は、膠原線維と呼ばれる物質が増え、皮膚や内臓の厚みが増していくことです。
気管支拡張症
気管支拡張症は、気管支の壁が炎症で破壊されることにより、気管支が拡張したままでもとに戻らないようになった状態を指します。
病変は比較的太い気管支に起こり、下葉に好発し、左肺にやや多い傾向があります。
咳や痰が多く見られ、時に血痰や喀血を生じることがあります。
気管支が慢性の炎症により壊れながら拡がってしまいます。
感染が起こりやすく、気管支炎、肺炎治療が多くなります。
胸部レントゲンやCT、痰の培養などにより長期的に管理を行うことが必要です。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群とは、眠っている間に呼吸停止、または低呼吸状態になる病気です。
その多くは、空気の通り道(気道)が塞がったり狭くなったりすることが原因です。
日本人の約5人に1人は睡眠に問題を抱えていると言われていますが、睡眠時の無呼吸になかなか気付くことができず、検査や治療を受けていない潜在患者も多くいると推計されています。
また、注意、認知、記憶などが障害されるばかりか、高血圧や脳梗塞、心筋梗塞のなどの原因の1つとも言われています。
一般内科
インフルエンザ
インフルエンザウイルスが病原で起こる疾患です。A型、B型、新型の3種類があります。
潜伏期は1~3日くらいで、咳をしたりするとウイルスが空中を浮遊し、それを人が吸い込むことで感染します。治療は症状出現後2日以内に開始します。
インフルエンザワクチンの予防接種である程度は防げますが、その年によって流行する菌の型が違うため必ず作用するわけではありません。
体の弱い人は、流行している時に人混みに出るのを控えた方がよいでしょう。
糖尿病
インスリンの異常から起こる病気です。
インスリンの産生や分泌が不足したり、インスリンが十分に働かなくなると、血液の中にブドウ糖が溜まり糖尿病の状態となります。
糖尿病を放置しておくと、網膜症、腎症、神経障害などの合併症が起こります。
食事療法や運動療法、薬物療法などをきちんと行い、血糖値をうまくコントロールして合併症を防ぐことが重要です。
脂質異常症(従来の高脂血症)
脂質異常症とは、血液中にコレステロールや中性脂肪などの脂質が異常に増加した状態をいいます。
長く続くと動脈硬化が生じ、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、 閉塞性動脈硬化症などの病気を起こします。
高血圧
血圧の高い状態を高血圧といいます。高血圧には特有な自覚症状はありません。
高血圧は長い時間をかけて進行し、血管を障害していきます。
その結果、動脈硬化を原因とした心臓病や脳卒中などの合併症の引き金となります。
高血圧と診断するには正しい血圧値の測定が必要です。
家庭血圧測定の正常値は収縮期血圧(上の血圧)が125mmHg、拡張期血圧(下の血圧)は80mmHg未満であり、同様に収縮期血圧135mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上を高血圧とされています。
メタボリックシンドローム
メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満の人が、
高血糖、高血圧、脂質異常といった生活習慣病の因子を2つ以上持っている状態をいいます。
メタボリックシンドロームは、自覚症状がないまま、動脈硬化を進行させて、やがて血管のトラブルを起こし、
心臓や脳に大きなダメージを与えるリスクが高くなります。
アレルギー科
アレルギー性鼻炎
アレルギー性鼻炎は、ハウスダストやダニ、花粉など体にとっては異物である抗原(アレルゲン)を鼻の粘膜から吸入することによって体の中に抗体ができ、何度か抗原を吸入しているうちに抗体が増え、やがてアレルギー症状が起こってくる病気です。喘息との関連もあります。
アレルギー性鼻炎には、通年性アレルギー性鼻炎と季節性アレルギー性鼻炎とがあります。通年性アレルギー性鼻炎のアレルゲンは、ハウスダストやダニ、ペットの毛、カビ、などで、一年中症状があります。もう一つの季節性アレルギー性のアレルゲンは、スギ、ヒノキ、ブタクサなどの花粉で、花粉症とも呼ばれます。花粉症の場合、目のかゆみ、涙目など目の症状を伴う場合が少なくありません。
じんましん(蕁麻疹)
じんましんは皮膚の肥満細胞から遊離した物質によって全身もしくは一部の皮膚に、大小さまざまな発疹が現われ、強いかゆみを伴う症状です。発疹は数分から数時間で消えてなくなります。
アレルギー体質の人に多く見られるとも言われますが、外部刺激やストレス、食品(サバ、エビ、卵など)などでも起きます。